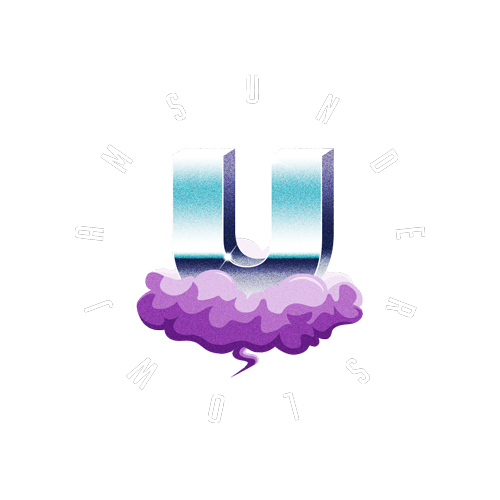underslowjams Web Openにあたり、
Amebreak 伊藤雄介氏によるunderslowjamsのインタビュー公開デス!
ヒストリー的な話から最新作「PHONETIC CODE」についてなど、
読み応えありなガッツリな内容です。どうぞw
“ヒップホップ・バンド”というと、アメリカではザ・ルーツのようなグループを多くのリスナーが思い浮かべるだろうし、日本のヒップホップでも、多くのグループがバンド・サウンド/生演奏を用いてヒップホップのグルーヴに挑んできた。だが、一言で“ヒップホップ・バンド”と言っても、そのサウンドの振れ幅は、サンプリング/打ち込みをベースに作られたプロダクションをバンド的解釈で再現するスタイルから、より自由な精神性で様々な音楽性を融合したミクスチャー・バンド的なスタイルまで、様々だ。
自らを“ヒップホップ・バンド”と位置付けるunderslowjamsもまた、雑多な音楽的バックグラウンドやアプローチを起点としながら、長年の活動を通して自らのスタイルを確立してきた、ユニークなグループだ。
underslowjamsの始まりは2004年にまで遡る。メンバーの出身地/地元、音楽の趣味やライフスタイルも異なる面々が東京で知り合ったことがきっかけだ。
「当時のtake-cの家が結構音を出せる場所で、DJのRYOTAがスクラッチをしてtake-cがギターやドラムを叩き、その上でフリースタイルをして遊ぶような場所だった。それが半年ぐらい続いて、みんなも若いながらの熱さがあったし、スタイルは違ってもそれぞれスキルがあったから、音楽性がバラバラでも集まってた。その内、『このメンバーでライヴ、出来るね』みたいな感じになって」(rag)
ア・トライブ・コールド・クエスト(以下ATCQ)をイメージして、take-cの自宅にあった色々なレコードを見ながら“under”“slow”“jams”というワードをノリで繋げていった結果、グループ名はunderslowjamsに決まる。結成当初のメンバーは、rag(MC)、keita(MC)、take-c(ベース/ドラム)、ryota(DJ)の4人。2004年末の初ライヴから数ヶ月が経ち、同じくtake-cの家に溜まっていたyoshiro(ヴォーカル)が加入する。この時点で、“ヒップホップ・バンド”云々以前にいちバンドとして見ても珍しい編成だが、彼らが志向したサウンドはヒップホップだった。
「ryotaの影響が大きいと思う。彼はヒップホップDJだったし、『Keepintime』(LAを拠点に活動するヒップホップDJと伝説的なジャズ・ドラマーがセッションした作品/映像)とかも好きだったから、『俺がドラムをやってryotaがスクラッチをやれば同じことが出来るじゃん!』ってなって。俺はミクスチャー寄りのバンドを学生のときに散々やってたから、その音楽性を経てのヒップホップ・バンドというアプローチだった。最初の頃のライヴでは俺はベースを弾いてたけど、ryotaがベーシストのdove-eraを連れてきて」(take-c)
「で、サポート・メンバーとしてギターとキーボードも入ってもらって、最終的には8人体制でライヴをやってた」(yoshiro)
彼らが活動を開始した2000年代中盤の国産ヒップホップ/日本語ラップ・シーンは、リップ・スライムやキック・ザ・カン・クルーといったグループがポップ・チャートを席巻し、ニトロ・マイクロフォン・アンダーグラウンドやキングギドラのようなハードコアなラップ・グループも商業的に成功を収めた直後の時期だ。アンダーグラウンドに目を向けると、関東ではMSCやスカーズのような強いストリート性を持ったグループが台頭してきた時代でもある。“ヒップホップ・バンド”という括りではLoop Junktionや韻シストのようなグループはいたが、マイノリティな存在だった。
「みんなの共通意識として『こういうスタイルにしよう』というヴィジョンはなかった。それぞれ、『こういう感じかな?』みたいに、フワッとしてた」(yoshiro)
音楽性に対しては漠然とした意識のままスタートしたunderslowjamsだが、恵比寿のライヴ・ハウス/クラブで、90年代~00年代の東京アンダーグラウンド・カルチャーに大きな影響を与えた「みるく」(2007年に閉店)で、ドラムン・ベースやヒップホップなどを軸としたパーティを開催していた「風の人」クルーと交流を深め、後にクルーに加入する。
「俺の小中時代の先輩が『風の人』のオリジナル・メンバーで、彼が『風の人』主催のパーティ『KOONI』のサブ・フロアでDJをやってたから、俺はドラムン・ベースDJのサイドMCで入ってて。その流れで、下のフロアでunderslowjamsのライヴをやらせてもらったらすごく盛り上がって。で、下のフロアで何回かやってて、気付いたら上のメイン・フロアでライヴをやってた」(rag)
ライヴ活動を通してグループの音楽性を固めていった彼らは、「あの時点であった曲を取り敢えず音源にしたいという気持ちが強かった(take-c)」というモチベーションを具現化すべく、高円寺のセレクト・ショップ:LOWTEX(現在はKICKS LAB.という店名で原宿に店舗を構えている)協賛の元、2006年に1stアルバム「HOT JAMS」をリリース。そして、2007年には2ndアルバムにしてメジャー流通作品「UNDERSLOWJAMS」をリリースする。
サポート・メンバーも含めると大所帯のバンド編成だったこともあり、「HOT JAMS」でのunderslowjamsサウンドは、現在のそれと比べるとよりジャム・セッション感が強い。音楽性の軸として感じ取れるのは、ATCQや(ATCQ擁する)ネイティヴ・タン勢に代表される、90年代初期のヒップホップが持っていたジャジー且つファンキーな空気感であり、初期の代表曲のひとつである“Zionの森”のような、レゲエに影響を受けたユルさも印象的だ。
そして、「UNDERSLOWJAMS」では「HOT JAMS」の路線をベースとしつつも、ドラムン・ベースなどのダンス・ミュージックの要素も強く、「HOT JAMS」以上に振れ幅のある音楽性となっている。各メンバーの異なる趣味を反映させようとした結果だと思われるが、その裏にはメンバー間の音楽性やグループ像の乖離も影響していたようだ。結果、「UNDERSLOWJAMS」をリリースしてわずか1年ほどでグループは活動休止となる。活動休止の直前には次作の制作も始めていたが、それも形になることはなかった。
「『自分たちがどういうヴィジョンでバンドをやっていくか?』という部分でつまづいた。今考えるとそんな大した問題じゃなくて、みんなで話し合いを重ねればもっと良いバンドになれたと思うんだけど」(yoshiro)
「メジャーというところに行って、自分が想像していたことと実際にやっていることの違いは、俺も感じていた。それで、良い曲が書ける気分にならなくて。メンバー間でギクシャクし始めたし、音楽に対する意見もぶつかり始めていた」(rag)
活動休止に伴い、個人的な事情などもありメンバーが3名離脱し、残ったのがrag/yoshiro/take-cの3人。だが、6人組のバンドとして活動していた彼らが3人組となったことで、「この編成ではライヴ活動が出来ない」と感じていた彼らは、なかなか活動再開に踏み切れなかった。
活動休止期間中は、ragとtake-cによるユニット:UNDER BROSがEP「UNDER BROS」(2010年)を発表し、yoshiroとtake-cはアコースティック・スタイルでライヴ活動を展開するが、グループとしての再始動は活動休止から2年経った2010年のこと。Manhattan RecordingsのA&Rの誘いを受けて作られたシングル“IN THE RAIN”とカップリング曲“いかれたBABY”(フィッシュマンズのリメイク)の発表まで待つことになる。
「大事だと思ってたのは、俺たちのことより抜けたメンバーのことで。他のメンバーにまた活動する旨を伝えたら、みんな応援してくれたから、『それならまたやれるね』ってなった」(rag)
だが、活動を再開したとは言え、これまでと編成が異なるため、新たな音楽性とアイデンティティを確立し直す作業は楽なモノではなかっただろう。また、お世辞にも早いとは言えない彼らの制作スピードもあり、活動再開後初となるアルバム「PHONETIC CODE」がリリースされたのは、“IN THE RAIN”発表から約6年が経過した2016年のことだ。その間に、“IN THE RAIN”でレコーディング・エンジニアを担当していたエンジニア/プロデューサーのSUIが加入し、新生underslowjamsは4人組のグループとなる。
「最初に彼らのレコーディング・エンジニアを依頼されたときに、『エンジニアだけでなくトラックのアレンジもやってほしい』と頼まれてたから、その当時からトラック制作に関してtake-cとやり取りをしていた。雰囲気的に彼とはウマが合うから、それで始めていって。俺も『underslowjamsのプロデュースをやりたい』という希望があったので、そこから一員として一緒にやり始めて」(SUI)
SUIが加入する前後の時期から「PHONETIC CODE」収録曲の制作が開始され、2014年頃にはアルバムの原型が形作られていく。制作当初に彼らが目指していた音楽性に関して、彼らはこう語る。
「フル・バンドではなくなったから生バンド・サウンドではない方向に持って行く、みたいな話はあった。その頃、俺はドラムン・ベースとかが好きになって、生バンドじゃない打ち込みのサウンドでも面白いモノが出来るという気持ちになっていた」(yoshiro)
「活動休止したぐらいから、俺らの中でドラムン・ベースが流行ったんだよね。だから、『そっちに振り切ろう』という話になった」(rag)
その結果、ドラムン・ベースやこの時期に流行り始めたダブステップなどの要素を取り入れて、「PHONETIC CODE」の原型は形作られていく。だが……。
「レコーディングが終わって、リリースに向けて動き始める前に考える時間があったので、アルバムを聴き込んで」(take-c)
「あるとき、急に『アレ?』ってなった。『なんか、パチンコ屋みたいなサウンドだな』って(笑)」(rag)
「2015年頃だとEDMとかダブステップとか、そういうビートが世間から求められているように感じていたけど、2016年に入ってよりヒップホップ的なサウンドへの揺り戻しの流れを感じていて。あと、彼らが元々持っていた要素を現代版として出してあげられたら、という気持ちもあった。制作当初の音楽性から変化した理由としてはそれがある」(SUI)
先行シングルとして7インチもリリースされた“酩酊”のサウンドを作り直したことが、「PHONETIC CODE」の最終的な方向性を決定付けたと彼らは語る。
「“酩酊”のモチーフとしてあったのは、ATCQ“BONITA APPLEBUM (HOOTIE REMIX)”。A&Rの提案を受けて作ってみたら、それがハマった」(take-c)
「最初はもっとエレクトロっぽい音楽性だったけど、作り直してみたら『スゲェunderslowjamsっぽいな!』って、みんなが思った。『アレ?なんで俺ら、こういうサウンドを止めたんだっけ?』って話になって(笑)。そのときに、『(ダンス・ミュージック寄りの音楽性だと)抜けた他のメンバーに悪いじゃん』って思うようになって。今までバンドでやってきたのに、4人組になったらエレクトロ・グループみたいになるっていうことに違和感が生じたから、生音主体のサウンドに戻した」(rag)
オリジナル・ヴァージョンの“酩酊”は、「PHONETIC CODE」に“酩酊 -迷彩ヒマラヤ mix”として収録されているが、制作当初の音楽性が確認できるのはこの曲ぐらいで、それ以外の楽曲のバック・トラックは全てイチから作り直したという。つまり、世に出ている「PHONETIC CODE」は、実質的には“リミックス・アルバム”ということになる。
だが、サウンド面をイチから見直すという作業が、結果的に新生underslowjamsの個性を生み出すことになる。「PHONETIC CODE」は、生演奏を担当するメンバーが減ったことにより打ち込みで作られた部分も少なくないが、生音らしい温かみや揺らぎのあるサウンドが前面に出ている。また、朝本浩文や彼がプロデュースしたUA、初期のMISIAなど、90年代後半にJ-POPシーンで盛り上がったアーシーなR&B的サウンドからの影響も強く感じられる。そして、シャーデーやアシッド・ジャズ、レゲエ/ダブなど、UK経由のサウンドからの影響も強い。90年代的な感覚をアップデートした音楽として表現しようとする試みは珍しいことではないが、「PHONETIC CODE」で聴ける音は、誰かがやっていそうで実は誰もやっていなかったアプローチであり、それ故にフレッシュなものとなっている。
そして、underslowjamsの音楽をより個性的なモノにしているのは、やはりyoshiroのヴォーカルとragのラップの存在だろう。yoshiroの情感溢れるウェットな歌唱スタイルと、ragがクール目に繰り出すラップは、サウンドに上手くフィットする一方、歌詞の内容に目を向けると、彼らの“素”が反映されたユルさやダメ人間振り(失礼!)が露骨に表われていて、その等身大の歌詞の世界観とメロウなグルーヴが絶妙なバランスで共存している。何せ、アルバムの冒頭曲“夜の色”からして「怠惰に怠惰を重ねたいんだ」というサビである。この点に関してはメンバー自身が誰よりも自覚的だ。
「フィクション/ノンフィクションが混在しているけど、全体の雰囲気で俺たちが普段送ってる生活感がそのまま出ている。ダメな部分も含め。誇張はしてないし、むしろ控えめなぐらいなんだけど。以前の体制だと、バンド・サウンドの中でもっとポジティヴなことを歌うという意識があったかもしれないけど、それだけじゃないダメな部分とか、俺たちのリアルが出ている」(yoshiro)
ragとyoshiroの魅力について、サウンド・クリエイター側であるtake-c/SUIはこう分析する。
「ragは“感覚派”。昔からフリースタイルが得意だったし『スゲェ言葉、出て来るな』という印象が強い。yoshiroは、“IN THE RAIN”以降、独特なリリックが増えてきた。“諦め”が入っているというか、ポジティヴというよりネガティヴなんだけど、それが重く聴こえないし、声質も加わって心地良い」(take-c)
「yoshiroは歌のタイミング感やスキルが凄いから、そこはもっと多くの人に知ってもらいたい。例えば、ダブル/トリプルでコーラスの歌声を重ねていくけど、そこがピッタリ合ってないと嫌がるし、合ってないことに自分で気付く。彼の理想はすごく高いところにあって、故にそこに到達できない自分が恥ずかしいと思ってるぐらいの人。ragは、良い意味でも悪い意味でも“お猿さん”というか(笑)。バンドって、マジメにやるだけじゃ面白くないし、長く続けられないところがあるけど、彼は愉快な部分を持ち込んでくれる。フワッとしたラップなんだけど、刺してくるところは刺してくるから、そこがスタイルとしては好きだな、という話はよくtake-cとしている」(SUI)
2016年の夏に「PHONETIC CODE」がリリースされ、その評判は徐々に口コミなどを通して広がっていく。メンバー自身も、リリース後のライヴでの反響などを受けて、自分たちの新しい音楽が受け入れられてきているという実感があるようだ。
「今は『この面子で音楽を作り続けなければいけない』という意識がすごいある。『PHONETIC CODE』が出来た時点では『次、どうなるんだろうな?』って思ってたけど、今はみんな、『また作ってツアーに行こうよ』っていう気持ちになってる」(rag)
前述したような制作ペースの遅さや、雑多が故に音楽面での個人的ブームが予告なく変化するunderslowjamsなため、「PHONETIC CODE」で打ち出された世界観が今後も受け継がれていくかどうかは、メンバー自身も分からないようだ。だが、確かなのは、彼らの結束力と友情は今後も変わることはないということだろう。
「とにかく活動を続けていきたい。『売りたい』とか、そういう“希望”を持つのもいいけど、『こんな音楽を作りたい』って“信念”こそ重要かと」(rag)
「underslowjamsの一員としている自分が、一番心地良い。無理がないというか。周りから何を言われたとしても、『いや、知らない』って突き返せるし、そうあるための場所。今後も大事にしていきたい」(take-c)
interview & text:Yusuke Ito(Amebreak)